私には運転免許が、ございません。理由は、視覚障害であります。どんなにテクノロジーが進化しようとも、さすがにこれは、どうにもならない。ですから私は、生まれてこの方、運転席に座ったことが一度もない──。あるのは常に、助手席、もしくは後部座席というポジション。それでも、これまで乗り継いだ車はかなりの数にのぼります。ここまで来ると、ただの車好きではなく、“見えないくせに車を語る男”として、一部界隈で知られるようになったわけであります。
最初に手に入れたのは、ホンダ・インテグラ Type R。走り屋の象徴のようなこのクルマを、何を血迷ったのか、“見えない男”がチョイスしたのであります。運転するのはもちろん、当時の彼女。私は助手席から、「今のシフトチェンジ、うまいね」などと、なぜか玄人ぶったコメントを連発しておりました。えぇ、今思えば完全に“何言ってんだマン”。自分でも恥ずかしくなるほどの、的外れ評論家でありました。
それでも赤城山や筑波山に繰り出しては、ドリフトまがいの走りを堪能し、駐車場ではそのままイチャつくという、若さゆえの愚行に明け暮れておりました。「減速もっと早く!」と叫びながら、心のなかでは「命だけはお助けを…」と神に祈る。助手席で命の綱を握られながらも、愛に燃える。そんな二律背反の青春を、私は確かに生きておりました。
続いて選んだのは、日産グロリア。VIPカーであります。なぜこれを選んだのか。理由は明快であります。「実家が裕福だったから、なんとなく合ってる気がした」…ただそれだけ。乗り心地が良くて、排気量が3000ccという数字がなんだか偉そうに聞こえた、それが決め手でした。ここでもやっぱり助手席。余裕ある走りに酔いしれながら、完全に「自分も何かを成し遂げた気になっているだけの人」状態であります。
その後、私は欧州勢に傾倒していきます。アウディTT、S5、RSQ3、RS5と、勢いに任せて4台連続で新車を購入。見えないくせに「このデザインが美しい」「エンブレムの並びが絶妙だ」などと、完全に“ブランド名で車を味わう男”と化しておりました。
特に惚れ込んだのが、いわゆる「バブリング音」。エンジンを吹かしたときの「パンッ、パンッ」という爆ぜる音にしびれて、私はもう、その場で「これにします」と即決したのであります。見えないけれど、音は聞こえる。むしろ、音だけが頼り。だから私は、鳴き声で車を選ぶオトコでもあったのです。
運転はもちろん、妻。助手席の私は、「今のコーナー、ちょっと膨らんでたんじゃない?」と小言を言い、妻からは「運転したことないくせに」とあっさり切り捨てられる。これが、我が家のデフォルトであります。そしてこのあたりから、妻がスピード違反で取り締まられる頻度が、地味に増えていきます。ドイツ車は、スピード感を感じさせない──つまり、気づいた時には、もうオーバーしていたということです。
それでも、アウディを運転する妻の背筋は、どこか誇らしげでありました。「俺が選んだ車に、妻が乗っている」──それだけで、私は助手席のプライドを保っていたのであります。
そして時代は変わり、家族が増え、さらに愛犬まで加わると、車選びの基準は一気に“広さ”へとシフトします。まずはトヨタ・アクア。燃費重視のこの車は、コンパクトながら意外と使いやすく、何より静か。ですがある日、外食中に車内で留守番していた愛犬が、車に戻った我々を待っていたのは……後部座席のシートベルト2本が、完全に食いちぎられていたという惨状。もはや芸術的なまでの咀嚼跡に、我が家全員が言葉を失いました。
その後に選んだのが、ホンダ・フィットシャトル。愛犬との移動に最適な後部座席と荷室の広さ。中古とはいえ、その使い勝手の良さは絶品でした。助手席は娘に譲り、私は愛犬とともに後部座席。そう、私はもう、完全に家族内ヒエラルキーの最下層に位置しております。ですが、犬に寄りかかられてうたた寝するその時間は、どんなスポーツカーにも勝る幸せであります。
ちなみに、フィットシャトルを購入してすぐの頃。まだ子犬だった我が家の愛犬が、駐車場で妻と娘を待っている間に、爆音を伴って下痢便を放出。その瞬間、あたりの車がピタリと静まり返り、私の中の時間も止まりました。今でも、あのときの「ブオォッ…ビシャッ」というサウンドは、私の脳内に鮮明に残っております。
続いて選んだのが、トヨタ・シエンタ。こちらも中古車で、愛犬との相性重視であります。スライドドアの利便性、フラットな荷室。どれをとっても、使い勝手が良い。そして現在も、我が家で現役バリバリの主力機です。
私は今も後部座席。愛犬と一緒にうたた寝し、いびきをハモらせております。車内に響き渡る私と犬の二重奏。もはや地響き。時折、車の異音と勘違いされるほどの共鳴っぷりに、通行人も首をかしげる始末であります。
さらに時代はキャンプブーム。アクアを所有していた頃、同時に手に入れたのが、メルセデス・ベンツ Vクラス マルコポーロ(並行輸入)であります。さらにその次にはキャンピングカーも導入。まさに「小さな移動する家」を2台も持つという、贅沢な時代を過ごしておりました。
とはいえ、アクアはどちらかといえば買い物や通院用の実用車。対してマルコポーロやキャンピングカーは、非日常への扉でありました。
そして現在の主力マシンが、トヨタ・ハイラックス。キャンピングカーでは物足りないと感じた妻が、完全に独断、完全に自腹で、荷台をDIY改造。キャノピーの装着、エアコン、電子レンジ、冷蔵庫、ポータブルバッテリー、大容量走行充電。あらゆる装備を搭載し、今ではちょっとした走る要塞に仕上がっております。
サービスエリアで電子レンジの「チン♪」が鳴るたびに、「これDIYですか?」と聞かれる妻。彼女はにこやかに「全部、私がやりました」と即答。えぇ、その通りでございます。私は資金も出しておりませんし、口すらほとんど挟んでおりません。せいぜい「いいじゃん、それ」とうなずいた程度。それでもなぜか、“見えないけど全部仕切ってる男”みたいに扱われ、勝手に“名誉監督”ポジションが確立されていきました。私は今、それに甘んじております。
免許はない。でも、車には物語がある。助手席や後部座席から見る景色だって、人生そのものなのであります。
「見えないのに、どうしてそんなに車が好きなんですか?」と聞かれたとき、私はこう答えています。
見えなくても、音や振動や匂いで、車は感じられる。
そして何より、「どんな景色を、誰と見るか」。それこそが、クルマという乗り物の、本当の価値ではないでしょうか。
私のカーライフは、まだまだ続きます。

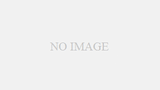
コメント