今日は自虐的な言葉を封印し、しんみりとした気持ちで書いてみます。
いまさらながら、ずっと心に引っかかっていることがあります。
それは、小学生のころに受けた知能検査の記憶です。
その検査は、音声に合わせて設問に答えていく形式でした。
ですが、私はそのスピードについていけず、まともに回答することができませんでした。
なぜそうなったのかといえば、視力の問題が大きかったと思います。
当時、検査の進行方法が弱視の子どもに配慮されたものではなかったことは、今振り返れば明らかです。
でも、当時の先生や保護者の間で、そうした視点からの検討がなされたのかどうかは分かりません。
色覚検査も同じように、引っかかっていました。
実際には、日常生活で赤と緑の区別はついていたのに、検査では「区別できていない」と判定される。
今なら、その原因が「距離」や「見え方」の問題だったことは想像できます。
弱視だった私は、模様や数字以前に、検査表自体がぼんやりして見えていなかったのです。
こうした経験は、後々の学業にも影響を与えました。
中学・高校・大学入試……どの段階においても、特に国語は、回答時間内に終わったことがほとんどなかったと思います。
学年が上がるほど問題の分量が増し、その傾向はより顕著になりました。
ほかの教科でも、時間が足りず、マークシートの択一だけでもなんとか埋めるということが続きました。
親には、自分の見えにくさや時間が足りないことを伝えていましたが、当時は個別の配慮が一般的ではなかったため、
親も学校側と話し合っても解決にはつながらないと考えていたのかもしれません。
今でこそ「合理的配慮」や「アクセシビリティ」といった言葉が当たり前になりつつありますが、
当時の教育現場には、そうした意識や制度はほとんどありませんでした。
与えられた条件の中で、ただ無理をして頑張るしかなかった、というのが正直なところです。
これは決して、「できなかったこと」の言い訳ではありません。
ただ、もしもっと早く配慮があれば、違った選択肢や可能性が広がっていたのではないかと、今でも時々考えてしまうのです。
同じように悩んでいる人がいるかもしれません。
声をあげづらい環境の中で、自分だけがおかしいのではと感じている方もいるでしょう。
そんな誰かにとって、少しでも「そうだったんだ」と思えるきっかけになればと思い、記録として残しておきます。

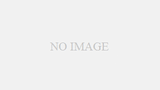
コメント